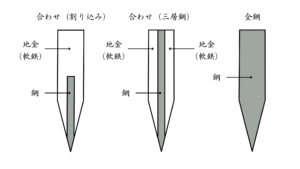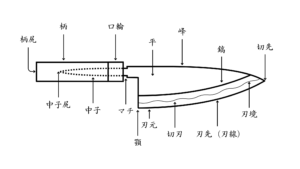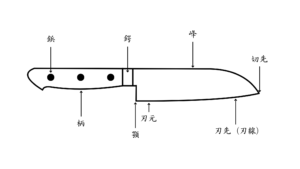YouTubeにて藤原先生が砥石の歴史について解説してくださったので、動画の内容をまとめていきたいと思います。
※あくまで歴史なので、100%正しい情報という受け取り方ではなく、こういう背景や考え方があったのではないか、という前提で楽しみながら見ていただければと思います。
反対に、これはこうなんじゃないか?という疑問や新しい考え方があればぜひ気軽にコメントしてくださいね♪
砥石はすべての「土台」
藤原先生は、包丁や切れ味を語る上で「砥石」が一番大切だと語っています。
もちろん包丁の形や鋼材の種類も大切ですが、砥石がすべての土台となっているとも言えるでしょう。
だからこそ、藤原さんご自身でも砥石の開発なども行っており、よりその重要性が見えてくるのではないかと思います。
ちなみにいつもですが、撮影を開始する前からお二人共、庖丁のお話しかしていないので、常にカメラを回していたい気持ちです🤣
それでは、砥石の歴史を見ていきましょう。
磨製石器時代:加工技術の転換点

磨製石器の時代、日本では約一万数千年前から続く縄文時代にあたります。
人々は定住生活を始め、狩猟や採集に加え、植物の栽培なども行うようになりました。
生活の道具が多様化する中で、従来の「石を叩いて割る」だけの打製石器から、石を擦って形を創り出す「磨製石器」へと人類の加工技術は大きく転換しました。
ここで初めて「割る」という段階を超え、「研ぐ」「磨く」といった形状を整える技術が成立しました。
石を目的の形にするために、石と石を擦り合わせるという行為こそが、現代まで続く「研ぎ」の原点とも言えます。
実際に、当時の遺跡から出土する石器に擦れた跡が確認されることから、この時代ではすでに石を研磨するための「砥石」に近い概念が存在し、活用されていたと推測されています。
砥石は「モノを作る」という面において、現代でも重要な役割を担い続けている道具です。
日常生活の中で砥石について深く考える機会は少ないかもしれませんが、人類の文明に極めて大きな影響を及ぼしてきたのは、紛れもなく「砥石」であり「研ぎ」の技術なのです。
砥石は決して刃物の付属品ではなく、人類の加工文化そのものを支えてきたスタート地点であったと言えます。
弥生時代:資源としての「流通」と「選別」

弥生時代は紀元前10世紀頃から紀元後3世紀中頃まで、約1300年にわたって続いた時代です。
それまでの狩猟採集中心の生活から本格的な稲作へと社会構造が大きく変化し、木材加工のための磨製石器が大量に必要とされるようになりました。
この時代、砥石は単なる石ではなく、特定の産地から運ばれる重要な資源となりました。
遺跡から出土する砥石を分析すると、その土地には存在しない種類の石が見つかる例があり、この時代にはすでに「良い石」を遠方から調達して消費地へ運ぶという、資源としての流通ルートが確立されていたと考えられています。
当時すでに、石と砥石の差を判断できる藤原先生のような方がいたのかもしれません。
磨製石器の時代からも、荒砥から中砥まで様々な砥石が取れていたと考えられますが、その中から「より早く削れる」といった道具としての性能によって、より厳格に選別されるようになったと考えられています。
こうした良質な砥石の確保は村の生産性に直結するため、石の性質を見極める確かな目と、それを安定して手に入れるためのネットワークは、当時の社会において極めて重要な役割を担っていました。
平安時代:品質の序列と「名前」の誕生

平安時代は、794年の遷都から12世紀末まで続く約400年間の時代です。
貴族文化が華開いた一方で、武士の台頭や鉄製道具の普及が進み、技術や美意識が洗練されていきました。
この時代、砥石が名前で語られ始め、品質による序列が明確になりました。
その代表が現在の愛媛県で採掘されていた「伊予砥」です。伊予砥がわざわざ都まで運ばれていたという記録は、当時すでに砥石の品質差が広く認識されていたことを示しています。
良い石には遠方から運ぶだけの価値があるという、道具に対する価値観が育まれた時代でした。石ころが砥石として認識され、さらに品質の差がはっきりしてきたことで、識別のための名前が生まれ、石に価値がついたと考えられます。
それまでは作業効率を重視した荒砥や中砥が中心であったと推測されますが、この時代にはすでに鉄器などの製造加工をする技術があり、その上でより鋭い切れ味や、それを引き出すための細かさを求めることができたのではないかと考えられます。
鎌倉時代:仕上げ砥石と日本刀

鎌倉時代は、1185年頃の幕府開設から1333年まで続く、武士が政治の主役となり力こそが正義となった時代です。
貴族中心の社会から武士が実権を握る武家社会へと大きく転換したことで、軍事産業が国の中心的な役割を担うようになりました。
この時代、京都の山で質の高い仕上げの天然砥石が数多く発見され、それらは天皇などに献上されるほどの貴重な資源として扱われていました。
当時、圧倒的な切れ味を引き出せる砥石の発見は、戦いにおける殺傷能力を飛躍的に向上させ、戦局を左右する軍事的な道具となりました。
その力は時として脅威となるため、砥石は厳重に管理されていたとされています。また、幕府が専任の鍛冶屋を抱えることで、その高度な技術も同時に管理していた可能性があるとも考えられます。
また、切れ味の追求と同時に「美」の意識が確立されたのもこの時代です。
天然の中砥では表面が白く霞んだような仕上がりになりますが、天然の仕上げ砥石を用いることで、今までにはない光沢が生まれるようになりました。
これによって日本刀特有の模様が鮮明に浮かび上がり、道具としての性能を超えた美の世界が切り拓かれました。
優れた砥石の存在が研ぎの技術を押し上げ、高まった技術がさらに道具の進化を促す。 どちらが先かは分からずとも、この優れた天然砥石という道具があったからこそ、現代に続く劇的な進化を遂げたのだと思います。
世界的に見ても、硬さや柔らかさなど様々なバリエーションがこれほど豊かな天然砥石が産出されるのは、ほぼ日本に限られます。 まさに、日本の研ぎ文化を象徴する奇跡的な環境といえるでしょう。
補足にはなりますが、一方でそのように技術を高めた刃物が、実際の戦場でどのように扱われていたかについては、現代の私たちが抱くイメージとは少し異なる現実があるかもしれません。
実際、合戦の主力は刀ではなく、弓矢や槍、のちの時代には鉄砲といった武器でした。
戦場で一番大事なのは射程距離と長さであり、集団で戦う場合、刀のような短い武器で突っ込むよりも、遠くから弓や鉄砲で撃ったり、長い槍で叩いたり突いたりする方が圧倒的に有利だからです。
当時の記録や絵巻物を見ても、足軽たちが槍で壁を作ったり、石を投げたりしている描写が多く、刀を振り回して一騎当千というのは、後世の創作や物語の影響が非常に大きいと考えられます。
では、刀は何だったかというと、現代でいう拳銃のようなサブウェポンとしての役割だったと推測されます。
槍が折れたり、矢が尽きたり、敵と取っ組み合いになった時の最後の手段として使われていました。また、倒した敵の首を最後にかき切るための道具としての役割も大きかったようです。
実際、傷ひとつない日本刀がこれだけ多く残っているということは、軍事的な武器と今の日本刀が違うという推測ができます。
戦国時代などの実戦刀は、美術品のような美しさよりも、頑丈さや切れ味が優先された消耗品でした。大量生産品も多く、使い捨てに近い感覚で扱われていたものもあります。
現在私たちが美術館で見るような美しく研ぎ澄まされた日本刀は、身分の高い武将が持っていた特注品や献上品など、精神的な意味合いが強くなってから作られたと考えられ、当時の泥臭い実戦用の武器とは少し性質が異なるのではないかという予測もできます。
江戸時代:泰平の世と「もったいない」の精神

江戸時代は、1603年から約260年間にわたって徳川将軍家が日本を治めた、長く平和が続いた時代です。
鎖国政策によって独自の文化が醸成され、街道の整備や商業の発展により、都市部を中心に庶民の生活水準が大きく向上しました。
江戸時代になって社会が安定し、ようやく大工道具や調理用の包丁が庶民の生活に深く根付きました。
幕府の御用砥を務めた「本阿弥家」が天然砥石の管理を任され、良いものは特権階級へ、そうでないものは一般へと流通し始めたことで、砥石の供給体制も整っていきました。
当時は資源が限られていたため、「もったいない」という精神が強く、道具を研いで直して長く使う文化が社会のインフラとして定着しました。
道具は単なる消耗品ではなく、手入れを繰り返しながら一生寄り添う「相棒」へと変化したのです。
食の分野においても、この頃にはすでに「柳刃は引いて切れ」「往復はダメ」といった技法が一般に広まっていたとされ、それだけ豊かな食文化が発展していたことが伺えます。
大きな戦乱がなくなった社会の安定が、ひとつの道具に手間暇をかける精神性と、職人や庶民のこだわりを育んだ時代であったと考えられます。
明治〜昭和初期:近代化と人造砥石の誕生

明治から昭和初期は、1868年の明治維新から1940年代の第二次世界大戦頃までの時代です。
武士の時代が終焉を迎え、文明開化とともに西洋の機械技術や工業製品が流入し、日本が近代国家へと急成長を遂げた激動の時代でした。
この時代、天然砥石の採掘が最盛期を迎える一方で、人造砥石の技術が登場します。
1890年代にアメリカで研磨剤が生まれ、1940年代には人工的に砥石を作り出せるようになりました。
良いものが安定して手に入らない「天然砥石」に対し、同じものを安定的に作れる「人造砥石」への移行は、大きな進化でした。
しかし、その裏で使いこなすために知識が必要な天然砥石は敬遠され、「人造があれば天然はいらない」と捨てられてしまうようなこともあったと言われています。
伝統的な職人の技と、効率を重視する近代的な工業化が激しくぶつかり合い、道具の価値観が根底から揺れ動いた時代であったと考えられます。
昭和後期〜平成:鋼材と砥石の逆転現象
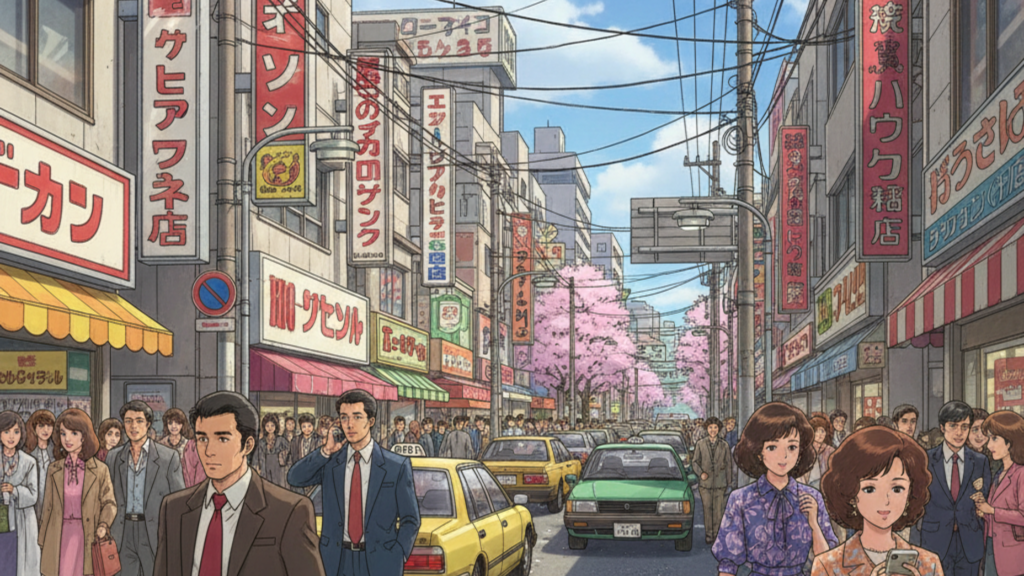
昭和後期から平成の時代は、1950年代の高度経済成長期から2019年頃の戦後の復興から経済大国への躍進を経て、大量生産・大量消費が一般化した成熟社会の時代です。
人造砥石の普及により、研ぎは職人の勘から再現可能な技術へと変化しました。
天然砥石では硬い鋼材を研ぎきることが難しかったのですが、人造砥石が進化し、より硬い鋼材も削れるようになったことで、この時代になってよくやく評価されるようになった鋼材があったのも事実です。
昔は存在する砥石に合わせて鍛冶屋が作るという形でしたが、今は精密な機械製造が可能になったため、包丁そのものの性能だけで完結してしまう側面もあります。その中で、使い手の声は届きにくくなり、自分で道具を直すという文化も同時に薄れてきたと感じる時代です。
そうした流れの一方で、最高の切れ味を求める環境においては、ダイヤモンド砥石の登場は革命でした。
特に面直しの道具として、それまで手間と時間がかかっていた砥石の歪みを短時間で正確に修正することを可能にしたのです。土台となる砥石の平面を容易に維持できるようになったことで、刃物の切れ味を引き出す精度は格段に向上しました。
世の中に使い捨てが増える反面、技術を突き詰める一握りの人々にとっては劇的な進化を遂げた時代であり、一般層と専門層との乖離が大きくなった時代と言えるのではないでしょうか。
最後に:多くの選択肢を選べる時代

かつてはモノを大切に長く使わざるを得ない環境要因もあり、道具を自分たちでメンテナンスすることが当たり前でした。しかし、現代は安価で質の良いものが量産されるようになり、より瞬間的なインパクトのあるモノが好まれる傾向にあります。
技術の向上により、一定のクオリティのものが容易に手に入るようになったことで、それなりのモノをそれなりに作れば特に困ることのない時代となりました。
現代の高度な技術発展は、もはや生命を維持するという目的を大きく上回っています。だからこそ、70点の美味しいものが簡単に作れてしまう世界において、あえて95点や96点という部分まで突き詰めるような人は、ほとんどいなくなっているのも現状です。
しかし、このように平和で満たされた時代だからこそ、一見すると意味があるのか分からないような「突き詰めた世界」が、新しい何かを見せてくれるという価値があるのではないでしょうか。
技術が発展し、より多くの選択肢を選べるはずの今、誰もが選ぶ「それなりの正解」で止まってしまうのは、非常に惜しいことだと考えます。
今は天然砥石も人造砥石も非常に高い水準にあり、歴史上もっとも切れ味を追求できる時代です。
道具を選べるということは、料理の味さえも選べるということです。
研ぎという文化が再び広まり、手間暇をかけるこの「奇跡」を大切にすることが、より豊かな未来の文化へと繋がっていくはずです。